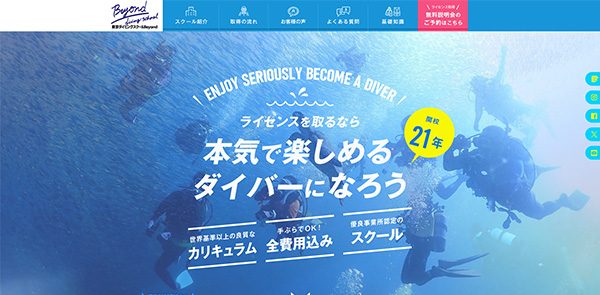ダイビング中に気を付けたい肺の過膨張障害とは
ダイビング中は体調の変化に気を付けながら、無理なく行うようにしましょう。ここではダイビング中に気を付けたい、肺の過膨張障害について紹介します。
ダイビング中になりやすい肺の過膨張障害とは
肺の過膨張障害とは、ダイビング中に起こる障害で重篤なものの1つです。ダイビング中に呼吸を止めた状態で浮上すると、肺の空気が膨張します。最悪の場合、肺胞が破裂してすぐに治療が必要です。
空気が肺と肋膜の間に漏れた場合、肺を圧迫して胸痛を感じるでしょう。また空気がもれて心臓や血管を圧迫すると、気が遠くなる・息苦しくなるという症状も起こります。
肺の過膨張障害には症状によって4つの種類があります。
- ・エアエンボリズム
肺の過膨張障害の中で最も深刻な症状です。肺の内部にある肺胞が破裂し、空気が血管内に入り込みます。脳血管に入ると意識不明やめまい、麻痺などが起こります。すぐに病院へ行き、治療が必要です。 - ・気胸
肺内の空気が膨張して肺が破裂し、空気が漏れて肺を押しつぶす症状です。ダイビングに限らず普段の生活でも起こり得る症状です。肺から漏れた空気を吸いだしたり、破裂した箇所を縫合したりという治療が行われます。 - ・縦隔気腫
肺が破裂したことで漏れた空気が縦隔に溜まり、圧迫してしまう症状です。自然治癒を基本としますが、漏れた空気を穿刺吸引して治療するケースもあります。 - ・皮下気腫
肺の過膨張障害の中では軽い症状です。肺から漏れた空気が首の下や鎖骨など皮の薄い部分に溜まります。
肺の過膨張障害になる原因
肺の過膨張障害になる原因は、呼吸(息)を止めたまま浮上することです。水中世界は、推進と比例するように圧力は強くなります。10m潜れば陸上の2倍、そして20m潜れば3倍と増えていきます。10mの段階で陸上と同じように空気を吸っても、半分しか吸えません。そのままでは息苦しくなってしまうため、レギュレータは水深ごとに適した呼吸圧の圧力で空気を供給できるように作られているのです。
水深10mであれば。陸上の際と比べて2倍の量の空気が供給されていることになります。しかし実際には量を2倍にしても吸いきれないため、密度を濃くして供給しています。
その密度が高い状態の空気を肺に入れたまま、息を止めて浮上しようとすると圧力が弱くなり、肺に入った空気は膨張します。空気の膨張に肺がついていけなくなり、結果として肺の過膨張障害を引き起こします。
深いところで息を吸うと肺は膨らみます。しかし水圧があるため、肺は周りから押されている状態なので、肺が膨らんでいても問題ありません。
しかし息を止めたまま浮上すると水圧が下がり、肺が一気に膨張してしまうのです。
肺の過膨張障害の予防策
肺の過膨張障害の予防策としてできることはただ1つ、呼吸を止めたまま浮上しない、ということです。
ダイビングの経験が浅いと、ついパニックになって息を止めたまま浮上しがちです。肺の過膨張障害を予防するために、まずは呼吸をせずに浮上すると肺の過膨張障害を起こす可能性がある、ということを理解し、絶対に息を止めないことを意識しましょう。
ダイビング中は「常に呼吸」を心掛けよう
ダイビング中、何よりも大切なのは常に呼吸をすることです。水中に潜る=息を止めるという認識を自然としてしまう人は多いですが、ダイビング中は何より呼吸を続けることが大切です。
ダイビング中は思わぬアクシデントも多くパニックになることがありますが、呼吸だけは絶対に忘れないようにしましょう。
- ライセンスで世界中の海が遊びのフィールドに!おすすめダイビングスクール
- 初心者も免許取立ての方も気になるスキューバダイビングQ&A
- ダイビングのNG行為「煙幕」とは
- ダイビングで気を付けること
- ダイビングで使うダイブコンピュータとは?
- ダビングでポイントへ行く時の船酔いの対処とは?
- ウェットスーツの下に着るインナー(水着)の選び方
- 初心者は知っておくべきダイビング中の鼻血と原因
- 妊娠中にダイビングはできるの?
- 喘息がある場合のダイビングにはどんなリスクがあるの?
- ダイビングスクルーは少人数制がよいといえる3つの理由
- ダイビング中に頭痛が起きた場合の対策はどうすればいい?
- ダイビングでの窒素中毒とは?窒素酔いの症状や予防法を紹介
- 60歳から東京で始めるシニアダイビングの5つの魅力
- 体験ダイビングで潜れる深さは?
- ダイビングは水深どのくらいまで潜るの?
- ダイビング中の迷子「ロスト」の対策
- ダイビング前後におすすめのストレッチ
- アクセサリーを付けてダイビングを行う際の注意点
- プール付きダイビングスクールを選ぶべき4つの理由
- かなづちや視力が悪くてもできる?
- スキューバダイビングの怖い体験と安全に潜るためのポイント
- ダイビングでのスクイズってなに?サイナススクイーズとの違いは?
- 良いダイビングスクールの選び方は?
- ダイビング後すぐに飛行機に乗るのはNG?
- ダイビングで雨が降った場合って決行できるの?
- 遠方(海外や沖縄)でライセンスを取ったんだけど?
- ダイビングのマスククリアとは?
- ダイビングに必要なスキル「中性浮力」とは
- ダイビング時の口呼吸のポイント
- 体験ダイビングでは何ができるの?
- 体験ダイビングは何歳から潜れる?
- 脱!ブランクダイバー~海に戻るのに大切なこと~
- ダイビングは冬でもできるの?
- ダイビングでタンクが外れたときの直し方
- ダイビングは持病・疾患があってもできる?
- オクトパスブリージング(バックアップ空気源の使用)のやり方
- ダイビング中にトイレに行きたくなったらどうすればいい?
- ダイビングで気を付けたい日焼け対策
- ダイビングを楽しむための準備とケア
- 潜る時間はどのくらい?減圧症ってなに?
- ダイビングコンピューターの使い方や注意点
- 東京のダイビングスクールの無料説明会に参加するべき理由5つ
- 器材は購入とレンタルどっちが得?
- 夜のダイビングの魅力と注意点
- ダイビングでよく使うハンドシグナルとは
- ダイビング中にサメに襲われることはないの?
- ダイビングで傷んだ髪の毛をケアする方法とは?
- ダイビングにログブックは必要?
- ダイビング中に起きる4つのトラブルとその対処法
- ダウンカレント
- ダイビングの基本ルール「バディシステム」とは?
- ダイビングの前に大切な耳抜きの方法とは?
- 都市型ショップとリゾート型の違いとは
- 快適なダイビングのためのウェットスーツ選び
- どんな危険生物がいるの?
- 生理の時でもダイビングは可能?
- ダイビングスクールのオンライン講習で基礎知識を学ぼう
- ダイビング当日もおしゃれはできる?
- ダイビングの受講に合った季節はいつ?